最近、本屋で『マンガでわかるAPD(聴覚情報処理障害)📘』という本を見つけました。
著者は阪本浩一先生です。
何気なく手に取ったのですが、気づけば最後まで読み切っていました。
そこに描かれていた内容は、まるで僕の過去そのものでした。
子どものころから感じていた「聞こえるのにわからない」
思い返せば、サッカーの試合中に監督の声が聞こえても、
何を言っているのか理解できないことが多かったです。
英語の授業でも、音は聞こえているのに意味が追いつかず、
頭の中で単語をつなごうとする前に次の音が流れていってしまいました。
みんなが笑顔でリスニングの答えを合わせている中で、
自分だけ取り残されていくような気がしていました。
大人になっても、それは変わりません。
会議で議事録を書こうとしても、理解する前に話が進んでしまい、
仕事の指示を聞いても、意味を整理する前に次の言葉が来てしまいます。
そして、🚗車の中では特に聞き取りが難しいです。
エンジン音や道路の反響が重なって、
相手の声が“音”としては届いても、“言葉”としては消えてしまいます。
特に、急に話しかけられたときの言葉は理解するのが難しいです。
相手が何を言ったのか一瞬で整理できず、
思わず「え?」と聞き返してしまうことが多いです。
たとえば、コンビニで店員さんに
「お箸や袋は要りますか?」と聞かれても、
音は聞こえているのに内容が頭に入ってこないことがあります。
一瞬のうちにいくつもの言葉が重なって、
何を聞かれたのか理解する前に会話が進んでしまうんです。
だから、つい聞き返してしまうこともよくあります。
気づけば会話がもう先に進んでいて、
そのたびに小さな焦りが胸の奥に生まれます。😔
耳が遠いだけだと思っていた
中学のころ、聴力検査で「高い音が少し聞こえづらい」と言われたことがありました。
そのときは、ただ単に耳が遠いだけだと思っていました。
「聞こえているのに理解できない」なんて、
そんなことがあるとは思っていなかったんです。
だから長い間、これは自分の集中力や性格の問題だと思い込んでいました。
APDという名前を知って
でも、この本を読んで初めて知りました。
「聞こえるのにわからない」には、ちゃんと名前があるということを。
それが**APD(聴覚情報処理障害)**です。
耳では音を拾えていても、脳がその音を整理して意味に変えるまでに
少し時間がかかる――そんな特性なのだそうです。
しかも、このAPDという症状は、ここ数年になってようやく知られるようになったものらしく、
まだ医療現場でも理解が進んでいる途中なのだそうです。
「聞こえるのに理解できない」という悩みを抱えたまま、
長い間苦しんでいる人も多いと書かれていました。
読んでいて胸が熱くなりました。💭
「ああ、僕は怠けていたわけじゃなかったんだ」と。
ただ、脳の情報処理の仕方が人とは少し違っていただけなんだと気づきました。
一対一の会話では何とか理解できるが、グループの会話や急な指示となると苦労するんです。
不思議だったんですよね…急に話を振られてみんなは何ですぐ答えられるんだろうって…
音感は悪くないのに
不思議なことに、僕は音感は悪くない方だ🎵と思っています。
人より少しだけ、音の高さやメロディを感じ取るのは得意なようです。
ただ、それに応えられる**ピアノの技術がまだ全然ないので、意味がない(笑)**のですが。
鍵盤の上で音を探しているうちに、せっかくの“音感”がどこかへ逃げていくような気がします。😅
これまで、音で覚えてピアノを練習していたため、楽譜が全然読めません。
まあ、もう5年前のことですが…。
最近になって、久しぶりに音楽を学びたくなり、楽譜の勉強の本📖を買いました。
ページを開くと、五線譜の中で音が静かに並んでいて、
「音を読むってこういうことか」と少しだけ納得しました。
たぶん僕にとっての“音”は、耳で聞くものというより、
目と心で感じるものなのだと思います。✨
静かな部屋で思うこと
今は神奈川のレオパレスで一人暮らしをしています。
手元に楽器が一つもないのが少し悩みです。
夜、ふと音を鳴らしたくなっても、
部屋の静けさだけが返ってきます。
それでも、本を開いて音符を見ていると、
少しだけ音の世界に戻れたような気がします。🎹
そしてふと思いました。
どうして僕の音感だけは正常なんだろうか?
言葉の聞き取りは苦手なのに、
音の高さやリズムには敏感でいられる――
人の脳って、本当に不思議です。
声を出せないこととの関係
**話を戻しますが、**思い返せば、気管切開で声を出せないことも、
どこかで関係しているのかもしれません。
人は、聞くことと話すことを繰り返しながら言葉を覚えていきます。
でも僕は、聞いた音を声で確かめることができませんでした。
「音を再現して覚える」という経験が少ない分、
きっと僕は“音の形”よりも“意味”で世界を理解してきたのだと思います。
だからこそ、読むこと📚が得意になりました。
読書をしていると、音の速さに追われることがありません。
自分のペースで、言葉を味わい、考えることができます。
文字の中には、僕にとっての“音のない会話”があります。
英語と日本語の違いに気づいたこと
最近、ようやく気づきました。💡
僕が英語でつまずいたのも、日本語を理解できるのも、
どちらも「脳の仕組みの違い」から生まれているということです。
日本語は、子どものころから慣れ親しんできた“脳が覚えている音”だから、
多少聞き取りづらくても、意味を予測して補えるのだと思います。
でも英語は、リズムもスピードもまったく違う世界。
聴覚処理に少し弱さがある僕にとっては、
最初の一歩でつまずくのが自然なことだったのかもしれません。
まだ「もしかしたら」の段階だけど
今のところ、病院で診断を受けたわけではありません。🏥
一冊の本を読んで、「もしかしたら」と思った段階です。
でも、自分の感じ方に名前があるかもしれないと知れただけで、
心がずいぶんと軽くなりました。
時間ができたら、病院で検査を受けてみたいと思っています。
原因を知るためだけでなく、
これからどう向き合えばいいのかを知るために。
文字で世界を聴くということ
僕は“聞こえにくさ”の中で育ちましたが、
その代わりに、“言葉を読む力”と“心で聴く力”を
手に入れたのかもしれません。
焦らなくてもいい。
世界の音が少し遠くても、
僕には“文字で世界を聴く”という方法があります。🐧
📚 参考
『マンガでわかるAPD 聴覚情報処理障害』
著:阪本浩一/法研
💬
ここまで読んでくださってありがとうございます。
同じように「聞こえているのに理解できない」と感じたことのある方がいたら、
こんな病気があるんだ!努力不足じゃないんだ!
と理解し、少しでも心が軽くなれば嬉しいです。
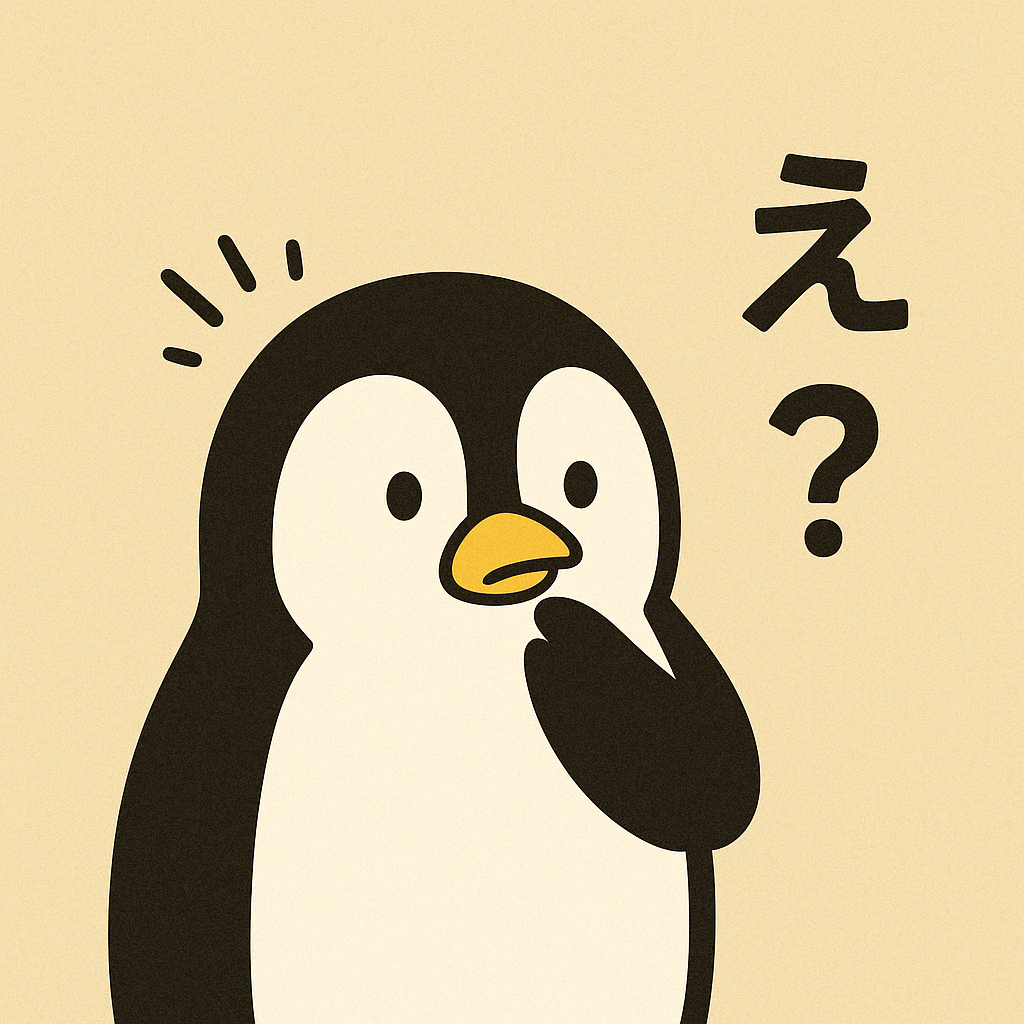
コメント